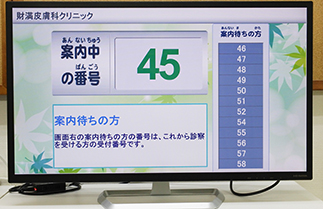財満皮膚科の治療件数ランキングBEST5
直近5年間について
当皮膚科クリニンクの治療件数を公開しています。
| イボ | ニキビ | 巻き爪 /陥入爪 | 爪水虫 | ほくろ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 (R7) | 3,419 | 2,290 | 1,361 | 737 | 601 |
| 2024年 (R6) | 3,579 | 1,937 | 1,067 | 721 | 617 |
| 2023年 (R5) | 3,714 | 1,730 | 1,007 | 831 | 618 |
| 2022年 (R4) | 3,404 | 1,603 | 1,128 | 737 | 477 |
| 2021年 (R3) | 3,165 | 1,568 | 998 | 662 | 478 |
○対象期間:2021年1月~2025年12月
(単位:件)
ニキビ・にきび
ニキビは、90%以上の人が経験するよく見られる皮膚の状態です。炎症がひどくなると、治療後に跡が残ることがあります。
そのため、ニキビができたら早めに医師に相談することが大切です。また、間違ったスキンケアを行うことで、ニキビが悪化することもあります。正しい知識を持って、早期の治療を心掛けましょう。
当皮膚科クリニックでは、日本皮膚科学会が定めたニキビ治療のガイドラインに基づき、アダパレンや過酸化ベンゾイル、抗生物質(飲み薬・塗り薬)を使用した治療を保険診療の範囲で提供しています。多くのクリニックもガイドラインに従った治療を行っていますが、実際に指示通りに治療を行っている患者は少ないとの報告もあります。当クリニックでは、患者様一人ひとりに合わせた治療を行うため、段階的なアプローチ(ステップアップ方式)を採用しています。
中年イボ(首イボ・スキンダック)
中年イボ(首イボ・アクロコルドン・スキンタッグ)は、首の周りなどにみられる小さな良性の皮膚症状で、アクロコルドンやスキンタッグと呼ばれることもあります。健康上の問題はありませんが、見た目が気になる場合や衣類とのこすれによる違和感がある場合は、除去や治療を検討することがあります。
当院では、保険診療の範囲内で、当クリニックオリジナルの専用機器を用いた冷凍療法を行っています。
この治療法は、比較的痛みが少なく、麻酔を使用せずに施術できます。施術後のケアや日常生活への影響には個人差がありますが、メイクや洗顔は施術後すぐに可能で、他の治療法(一般的な冷凍療法やレーザー、電気メスなど)に比べて跡が残りにくいことが特徴です。治療の適応や方法は、患者さまの状態に応じて医師が判断いたします。不安な点があれば、専門医に相談することをお勧めします。
多汗症(たかんしょう)
多汗症(たかんしょう)は、汗をかく量が異常に多くなる病気です。汗をかきすぎることで、学校や友達との遊び、部活動、会社などの普段の生活に支障が出ることがあります。
当院では、次のような治療を行っています。
1. 全身に汗をかく場合
・その場合、飲み薬(内服薬)を使って治療します。
2. 手のひらや脇の下に汗をかく場合
・そんなときは、塗り薬(外用薬)を使って治療します。
3. 手のひらや足の裏に汗をかきすぎる場合
・この場合、イオントフォレーシスという機械を使って、電気で汗を抑える治療を行います。
治療方法は、その人の症状に合わせて医師が最適な方法を提案します。多汗症でお悩みの方は、皮膚科専門医にご相談ください。
蒙古斑(もうこはん)
蒙古斑(もうこはん)は、赤ちゃんのお尻や背中に現れる青アザで、ほとんどの赤ちゃんに見られる自然な現象です。生まれてすぐから2歳頃まで、青色がはっきりと見えますが、その後、だんだん色が薄くなり、10歳前後にはほとんど見えなくなります。しかし、まれに大人になっても残ることがあります。
蒙古斑は通常、痛みやかゆみなどの症状を伴うことはなく、特に心配する必要はありません。蒙古斑は主に赤ちゃんのお尻や背中に現れますが、まれに腕や足、お腹、胸などにも現れることがあります。このような場所に現れるものは「異所性蒙古斑」と呼ばれます。
異所性蒙古斑は、年齢が進んでも消えないことがありますが、基本的には特別な治療は必要ありません。もし、蒙古斑が気になる場合や消えない場合には、Qスイッチレーザーが効果的です。当クリニックでは、Qスイッチ・アレキサンドライトレーザーを用いて治療を行っております。この治療は保険診療が適用されるので、費用面でも安心です。蒙古斑について不安なことがあれば、皮膚科専門医に相談されることをお勧めします。
太田母斑(おおたぼはん)
太田母斑(おおたぼはん)は、顔に現れる青アザのことです。この青アザは自然に消えることはなく、放っておいても改善しません。太田母斑は、皮膚に色素が沈着することが原因で起こります。治療には、Qスイッチレーザーが効果あります。
当皮膚科クリニックでは、Qスイッチ・アレキサンドライトレーザーを使って治療を行っています。一人ひとりの状態に合わせた治療を提案していますので、太田母斑が気になる場合は、皮膚科専門医に相談して、適切な治療法を選ぶことをお勧めします。
外傷性異物沈着症(鉛筆が刺さったり、擦り傷後に色が残った状態)
外傷性異物沈着症(がいしょうせいいぶつちんちゃくしょう)は、例えば鉛筆が刺さったり、擦り傷を作った後に皮膚に色素が残ってしまうことで生じる病気です。治療方法として、Qスイッチレーザーが効果的な場合があります。
治療方法や効果については個々の症例に応じて異なりますが、当皮膚科クリニックでは、Qスイッチ・アレキサンドライトレーザーを使った治療を行っております。もし、色素沈着が気になる場合は、皮膚科専門医に相談して、詳しい治療方法を確認することをおすすめします。
粉瘤(ふんりゅう・アテローム)
粉瘤(ふんりゅう・アテローム)は、皮膚の中に小さな袋のようなものができ、その中に皮膚から分泌される物質がたまることで発生する良性の腫瘍です。
多くは無症状ですが、たまに炎症を起こし、腫れて痛みを感じることがあります。軽い炎症の場合、抗生物質を使った飲み薬で治療します。しかし、炎症が進むと膿がたまることがあり、その場合は皮膚を少し切って膿を取り出す必要があります。
根本的な治療は、粉瘤ができた場所や大きさによって決まります。主に手術が必要で、袋状の部分を取り除きます。手術は局所麻酔をして行うので、手術中は痛みを感じることなく治療を受けられます。手術は、表面の皮膚を紡錘形に切開して、粉瘤の袋部分だけを取り出します。手術後は、傷口が乾燥しないように注意が必要です。
当院でも日帰り手術を行っておりますので、粉瘤でお悩みの方は皮膚科専門医にご相談ください。
ほくろ・ホクロ
ほくろ・ホクロは、皮膚にある色素を作る細胞(母斑細胞)からできる、良性の皮膚の腫瘍です。
多くの場合、特に問題はありませんが、ホクロに似た症状のものの中には、まれに皮膚癌であることがあります。ですので、自己判断せずに、皮膚科の専門医に相談して、正確な診断を受けることが大切です。もし除去したい、ホクロが気になる、または変化が見られる場合は、早めに診察を受けることをおすすめします。
ほくろ・ホクロの治療方法には、手術やレーザー治療などの方法があります。
治療法は、ホクロの大きさや形など、症例に応じて適切な方法を提案いたします。ホクロに関するご相談や不安がある場合は、皮膚科専門医にご相談ください。
尋常性白斑(じんじょうせいはくはん)
尋常性白斑(じんじょうせいはくはん)は、皮膚の色を作る細胞「メラノサイト」が減ったり、なくなったりすることで、皮膚に白い斑点が現れる病気です。この病気になると、皮膚の色が部分的に白く抜けていきます。白斑ができる場所は、体のどこでも起こる可能性があります。
当皮膚科クリニックでは、尋常性白斑の治療に「外用療法」(皮膚に塗る薬)や「ナローバンドUVB治療」(特殊な光を当てる治療)を行っています。治療方法は、患者様一人一人の症状に合わせて適切に選びます。白斑が気になる場合は、早めに皮膚科専門医に相談し、個別に合わせた治療を受けることをお勧めします。
老人性イボ(老人性疣贅・脂漏性角化症)
老人性イボ(脂漏性角化症)は、加齢に伴って皮膚に現れる良性のイボのことです。
通常は無害ですが、見た目が気になることがあります。このイボは、皮膚に小さなできものとして現れることが多く、色は茶色や黒色をしています。治療や除去はイボの大きさや状態、患者様の希望に応じて最適な方法をご提案します。お悩みの方は皮膚科専門医にご相談されることをお勧めします。
当皮膚科クリニックでは以下の治療法を行っております。
1. 液体窒素による冷凍療法(保険診療適応)
・液体窒素を使ってイボを凍らせます。複数回行うことによりイボが徐々に小さくなり、自然に取れていきます。
2. 炭酸ガスレーザー(保険診療適用外)
・より精密にイボを1回で除去する方法です。
3. 手術(保険診療適用)
・大きなイボや治りにくいものには、外科的に取り除く手術を行うことがあります。
尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)
尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)は、最もよく見られる「イボ」の一種で、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスが皮膚に感染することによって発症します。
イボは、感染した部分に硬いできもの(イボ)が現れます。通常、痛みはありませんが、見た目が気になることがあります。
現在、イボに対して「これで必ず治る」という特別な薬や治療法は確立されていませんが、液体窒素を使った治療法が一般的に行われています。
この方法では、イボの部分を凍らせて取り除きます。しかし、1回の治療で完全に治るわけではなく、何回か治療を受ける必要があることがあります。また、治療後にイボが再発することもあります。イボが気になる場合は、皮膚科専門医に相談して、あなたに合った治療方法を選んでもらうことをお勧めします。
水イボ(伝染性軟属腫)
水イボは、伝染性軟属腫ウイルスというウイルスが皮膚で増えることによって起こる病気です。
主に、小さなイボが皮膚に現れます。水イボ自体にはかゆみはありませんが、湿疹が周りにできたり、治りかけのときにかゆみを感じることがあります。水イボは、皮膚を掻いたり、触った手で他の場所を触ったりすると、ウイルスが広がってしまいます。さらに、ウイルスがついている物(タオルやおもちゃなど)を使うことでも、感染が広がることがあります。感染してから症状が出るまでに、14~50日の間の潜伏期間があります。
水イボは、通常半年から2年ほど(約1年で90%)で免疫ができて自然に治ります。治療や除去を希望する場合は、麻酔テープを使って痛みを感じにくくしてから、専用のピンセットでイボを取る方法があります。もし水イボを除去したい、水イボが気になる場合は、早めに皮膚科専門医に相談し、適切な治療方法を選んでいただくことをお勧めします。
タコ・魚の目
タコや魚の目は、足や手などの皮膚に何度も圧力や摩擦(こすれること)がかかると、皮膚が固くなってできるものです。
これは、皮膚が外からの刺激から身を守ろうとしているため、体が自分を守るために自然に反応した結果です。
治療を始める前に、まずはその刺激の原因を取り除くことが大切です。例えば、足にぴったり合った靴を選ぶことが重要です。しかし、タコや魚の目ができやすい人の中には、「靴がきついから」といって、緩めの靴を選ぶことがあります。でも、靴がゆるすぎると、足が靴の中で動いてしまい、歩くたびにずれて摩擦が起こって、かえってタコや魚の目ができやすくなることがあります。さらに、靴が足に合っていても、靴ひもをゆるめたままで履くと、足が安定せず、皮膚に余分な負担がかかってしまいます。
靴を選ぶときは、必要なら靴の専門家(シューフィッター)に相談したり、インソール(靴の中敷き)やフットケア製品を使うことも効果的です。もしタコや魚の目がひどくなったり、治らなかったりしたら、病院で適切な治療を受けることが大切です。気になる症状があれば、皮膚科専門医に相談してみましょう。
蕁麻疹(じんましん)
蕁麻疹は、皮膚が突然赤く盛り上がって、しばらくすると跡が残らずに消える病気です。
大抵は強いかゆみを伴い、チクチクした感じのかゆみや、焼けるような感覚が生じることもあります。通常、皮膚に現れた赤みやブツブツは、数十分から数時間で消えていきます。もし、現れたブツブツが何日も残って、特に後から茶色くなったり、ガサガサ、ポロポロするようなら、蕁麻疹ではなく別の病気の可能性があります。
蕁麻疹は、体内でヒスタミンという物質が働くことによって、血管や神経に影響を与え、症状が出ます。治療には、主にヒスタミンの作用を抑える飲み薬(抗ヒスタミン薬)が使われます。この薬を飲むことで、症状を和らげることができます。外用薬(塗り薬)はあまり効果がないことが多いです。
水虫(足白癬/あしはくせん)
「足がかゆい=水虫」とは限りません。
水虫だと思って皮膚科を訪れる患者さんの約半分は実際に水虫ですが、残りの半分は水虫以外の皮膚病です。自己判断で水虫と決めつけて市販薬を使用するのではなく、まずは皮膚科で「本当に水虫なのか」を確認することが大切です。
水虫(足白癬/あしはくせん)は、皮膚糸状菌というカビ(真菌)によって引き起こされる感染症です。
診断は顕微鏡検査で行い、白癬菌が確認されれば水虫と診断されます。もし白癬菌が見つからなければ、他の病気である可能性があり、その場合、治療方法も異なります。診断を受ける前の注意点として、2週間以上薬を使用しないようにしてください。
水虫が疑われる場合は、皮膚科専門医に相談し、正しい診断を受けることをお勧めします。
爪水虫(爪白癬/つめはくせん)
爪水虫(爪白癬/つめはくせん)は、爪にカビ(真菌)が感染して起こる病気です。
白癬菌というカビが皮膚から爪の中に入って、爪の下の部分にある角質を増やし、爪が厚くなったり、色が濁ったりすることがあります。このような症状は、白癬菌が原因だけではなく、他の原因でも起こることがあるため、まずは爪の濁った部分を調べることが大切です。
診断方法:爪が濁っている場合、白癬菌が原因かどうかを調べるために、爪の一部を少し取り、顕微鏡で確認します。この検査で白癬菌が見つかれば、爪白癬だと診断されます。
治療方法:爪白癬には、いくつかの治療方法があります。
1. 外用薬(塗り薬):爪の表面に塗る薬があります。
2. 内服薬(飲み薬):この薬を飲むときは、肝臓に影響が出ることがあるので、定期的に血液検査をして肝機能を確認します。
早期治療:もし爪が変だなと思ったら、早めに皮膚科専門医に相談することをお勧めします。正しい診断と治療を受けることで症状の悪化を防げます。
尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)
尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)は、皮膚に炎症が起き、皮膚の表面を作る細胞が異常に早く作られることが特徴の病気です。
これにより、皮膚に赤い発疹が現れ、その上に銀白色のフケのようなものがついて、ポロポロと剥がれ落ちます。乾癬ができやすい場所は、爪、頭、肘、膝、股、腰、お尻、すねなど、皮膚が擦れやすい部分です。
乾癬は、免疫の働きがうまくいかなくなることで起こります。発疹ができることでかゆみや痛みを感じることもありますが、症状の強さや場所は人それぞれです。
当皮膚科クリニックでは、乾癬に対して以下の治療方法を行っています
• ビタミンD3外用薬:皮膚の新陳代謝を正常に戻し、乾癬の症状を良くします。
• ステロイド外用薬:皮膚の炎症を抑え、かゆみや赤みを軽くします。
• ナローバンドUVB療法:紫外線を使って皮膚を治療し、乾癬の症状を改善します。
乾癬が気になる場合は、早めに皮膚科専門医に相談し、自分に合った治療方法を見つけることが大切です。
とびひ(伝染性膿痂疹・でんせんせいのうかしん)
とびひ(伝染性膿痂疹)は、皮膚に細菌が感染する病気の一つです。
この病気を引き起こすのは、主に「黄色ブドウ球菌」や「溶血性レンサ球菌」と呼ばれる細菌です。虫に刺されたり、汗をかいてできたあせもなどの傷口から、これらの細菌が皮膚に入り込み、感染が広がります。掻きむしった手を介して、あっという間に全身へ広がる様子が、火事の火の粉が飛び火することに似ているため、「とびひ」と呼ばれています。とびひの症状が出た場合は、病院で診てもらうことが大切です。
医師は、症状に合わせて、抗菌薬を飲んだり、塗ったりする治療を行います。ただし、治療方法はその人の症状や状態によって異なりますので、医師の指示をしっかりと守ることが大切です。
症状が気になる場合は、早めに皮膚科専門医に相談しましょう。症状の進行や治療にかかる時間には個人差がありますので、早期に治療を受けることが大切です。
脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)
脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)は、皮膚の油分(皮脂)が過剰に分泌されることによって起こる病気です。
紫外線やカビ(マラセチア菌)などの影響で、皮脂が分解されて皮膚に炎症を引き起こします。その結果、皮膚が赤くなったり、かゆみが生じたり、フケのような白いかさぶた(鱗屑)が見られることがあります。
脂漏性皮膚炎の原因としては、入浴、洗顔をきちんとしないことで皮脂が溜まることがあります。予防するためには、低刺激の石鹸やシャンプーを使って毎日髪を洗い、患部を優しく洗うことが大切です。強く擦らないように気をつけてください。また、皮脂や鱗屑を取り除くことも重要です。
生活習慣やストレス、食生活(特にビタミンBの不足や栄養バランスの乱れ)も影響しますので、規則正しい生活を送ること、十分な睡眠をとることが予防につながります。ホルモンバランスの乱れも原因になることがあるため、健康的な生活習慣を保つことが大切です。もし脂漏性皮膚炎が気になる場合は、早めに皮膚科専門医に相談し、適切な治療を受けることをおすすめします。
ジベル薔薇色粃糠疹(じべるばらいろひこうしん)
ジベル薔薇色粃糠疹は、主にお腹や背中などの体幹に赤い斑点(紅斑)が多数みられる皮膚の病気です。
症状としては、発熱や強いだるさなどの全身症状はあまり見られず、かゆみも比較的軽いことが多いです。10代から30代の比較的若い年代の方にみられることが多く、季節では冬場にかけての発症がやや多いとされています。
発疹は、やや横長の楕円形で、中央がカサカサになることがあります。この疾患は多くの場合、特別な治療をしなくても、時間が経つと自然に治ります。ただし、症状や経過について気になることがあれば、皮膚科専門医に相談することをおすすめします。
花粉皮膚炎
花粉が肌に付着することによって起こる炎症反応を花粉皮膚炎といいます。
特に、目の周りやあご、首など、外に出ている部分の肌に赤みや痒みが見られることがあります。
上まぶたが赤くなり、乾燥してカサつくことがあります。さらに、肌に軽い刺激を感じたり、乾燥により肌が粉をふくこともあります。
ただし、人によって症状の現れ方は異なりますので、気になる場合は皮膚科専門医に相談し、適切な対処法を確認することをおすすめします。
口唇ヘルペス
口唇ヘルペスは、単純ヘルペスウイルスというウイルスが原因で起こる病気です。
ウイルスに感染した後、体の中の神経に潜んで、体の抵抗力や免疫機能の低下などがきっかけで再発することがあります。再発の原因としては、風邪や疲れ、紫外線(日焼け)やストレス、さらには病気の治療で使う薬(抗がん剤や免疫抑制薬など)も影響します。これらのことが体の免疫力を下げ、ヘルペスが再発しやすくなります。口唇ヘルペスが再発しそうな兆候や、発症したと感じたときは、早めに治療を始めることで症状が軽くなります。
治療には抗ウイルス薬が効果的ですので、症状が出たら、早めに皮膚科専門医に相談し、適切な治療を受けることをおすすめします。
帯状疱疹(たいじょうほうしん)
帯状疱疹(たいじょうほうしん)は、体の左右どちらか一方の神経に沿って、ピリピリと刺すような痛みが起こり、その後に赤い斑点と小さな水ぶくれが帯のように広がるのが特徴的な病気です。
帯状疱疹は、通常、人生で一度だけ発症し、再発することはまれです。水痘・帯状疱疹ウイルスというウイルスが原因となって発症しますが、このウイルスは、子供の頃にかかる「水ぼうそう」を引き起こすものと同じです。
水痘・帯状疱疹ウイルスは、体内に残り、免疫力が下がったときに帯状疱疹を引き起こすことがあります。免疫力が低下する原因として、加齢やストレス、過労などが挙げられます。皮膚の症状(赤い斑点や水ぶくれ)が治ると、痛みも通常は治まります。しかし、症状がひどくなったり、痛みが強かったりする場合、特に夜眠れないほど痛い場合、また60歳以上の方では、痛みが長く続くことがあります。
治療には、抗ヘルペス薬という薬を1週間程度飲むことが一般的です。早めに治療を始めることで、痛みが長引くリスクを減らすことができます。
手荒れ(手湿疹)
手荒れ(手湿疹)は、手に触れる物質やアレルギー反応が原因で、手の皮膚が赤くなったり、かゆくなったりする病気です。
特に、洗剤やシャンプー、ハンドソープなどに含まれる成分が原因となることが多いです。また、手を何度も洗ったり、乾燥したりすると症状が悪化することがあります。職業による影響もあります。例えば、美容師が使う毛染めや香料、医療・介護関係で使われるゴムや消毒薬、花を扱う仕事で触れる花粉などが原因となることがあります。
手湿疹を予防するためには、水仕事や入浴後に手をよく乾かし、ハンドクリームで保護することが大切です。もし、ハンドクリームを使っても改善しない場合は、ステロイドなどの薬が必要になることがあります。手湿疹が長く続く場合は、早めに皮膚科専門医に相談して、適切な治療を受けることをお勧めします。
酒さ(しゅさ、赤ら顔)
酒さ(しゅさ)は、顔に赤みが出たり、ニキビのようなものができる皮膚の病気です。
「赤ら顔」とも呼ばれることがあります。また、顔がほてったり、ヒリヒリとした感じがすることもあります。酒さの原因は一つではなく、遺伝や生活習慣、ストレスなど、いろいろなことが影響しています。そのため、治療を始めてすぐに症状がよくなるわけではなく、症状が良くなったり、悪化したりすることがあります。
酒さを治すためには、根気よく治療を続けることが大切です。もし、顔の赤みやニキビのような症状が気になる場合は、皮膚科専門医に相談して、適切な治療を受けましょう。
自家感作性皮膚炎(じかかんさせいひふえん)
自家感作性皮膚炎(じかかんさせいひふえん)は、体の一部に強い皮膚炎(例えば湿疹やただれ)ができた後、その部分に対してアレルギー反応が起こり、発疹が最初にできた場所から全身に広がる病気です。
発疹は、小さな膨らみ(丘疹)として現れ、強いかゆみや痛みが伴うことがあります。これらの症状を放っておいたり、間違った治療をすると、症状がひどくなり、発疹が全身に広がることがあります。発疹が広がると、夜も眠れないほどのかゆみや痛みを感じることがあり、日常生活にも大きな影響が出ることがあります。
自家感作性皮膚炎は、年齢に関係なく発症することがあり、治療に時間がかかる場合もあります。
症状がひどくなる前に、早めに皮膚科専門医に相談して、適切な治療を受けることが大切です。
貨幣状湿疹(かへいじょうしっしん)
貨幣状湿疹(かへいじょうしっしん)は、皮膚が乾燥したり、虫に刺されたり、金属アレルギーなどが原因で起こることがあります。
この病気では、湿疹が次第に大きくなり、茶色っぽいコインの形をした湿疹が、特に膝から下に現れることが多いです。貨幣状湿疹は、症状が続くと「自家感作性皮膚炎(じかかんさせいひふえん)」という別の皮膚症状を引き起こすことがあります。
症状が現れた場合は、早めに治療を受けることが大切です。症状がひどくなる前に、皮膚科専門医に相談することをおすすめします。
頭ジラミ
頭ジラミは、特に子どもたちの間でよく見られる小さな寄生虫です。
東京都のデータによると、1歳から11歳までの子どもが頭ジラミにかかることが多いと言われています。
頭ジラミがうつる原因:頭ジラミは、体を近づけたり、頭をくっつけて遊んだりすること、またはブラシを共有することが原因でうつります。例えば、髪を一緒にとかしたり、寝具を共用したりすることがあると、頭ジラミがうつることがあります。不十分な洗髪も、頭ジラミが発生する原因となります。
毛虫皮膚炎
毛虫皮膚炎で最も多く見られるのは「チャドクガ」によるものです。
チャドクガは、ツバキやサザンカ、オチャなどの庭にある木の葉を食べる毛虫で、これらの木は公園やマンションの中庭にもよく見かけます。そのため、日常生活の中で一番身近な毛虫皮膚炎の原因はチャドクガが多いです。
チャドクガの毛虫は、関東地方では年に2回、5月から6月、そして8月から9月にかけて卵からかえり毛虫になります。1匹の毛虫には何十万本もの細かい毒針毛があり、これに触れると、その部分に赤いプツプツした発疹が現れ、強いかゆみを引き起こします。もし毛虫に触れたり、かゆみや発疹を感じたら、すぐに病院で診てもらうことをお勧めします。早めに対応することで、症状がひどくなるのを防ぐことができます。